自分を責める日々に、終わりを
「このままじゃダメ」「また失敗した」。
そんなふうに、自分にダメ出しをするクセはありませんか?
誰かに強く否定されたわけでもないのに、
自分で自分を否定し続けてしまう。
それが積み重なると、いつしか「自分を好きになる」感覚さえ分からなくなります。
けれど、**自己受容(じこじゅよう)**とは、
「完璧な自分」を受け入れることではありません。
むしろ、「うまくいかない部分」も含めて、自分にOKを出すことです。
ここでは、心理学にもとづいた自己受容のやり方を、実践しやすい形でご紹介します。
自己受容がうまくいかない本当の理由
努力しているのに、なぜか自分に満足できない。
そんなとき、多くの人は「もっと頑張ればいい」と思いがちです。
でも、実は**「頑張りすぎ」が自己否定を強めてしまう**こともあります。
よくある原因
- 他人の期待に応えようとしすぎている
- 自分の感情よりも「正しさ」を優先している
- 幼いころから「いい子」でいることを求められてきた
これらはすべて、「本音を無視する」習慣につながります。
自分の声を置き去りにしたままでは、どんなに成長しても満たされません。
自己受容のやり方【3つの習慣】
ここからは、実際に自己受容を進めるための習慣を紹介します。
どれも今日から始められる、小さなステップです。
① まずは「今の自分」に気づく
最初のステップは、自分の状態をそのまま観察することです。
やること:
- 毎日1回、自分の感情をメモする
- その感情がどこから来たか考えてみる
- 「そう感じたんだね」と自分に声をかける
例:
今日は上司に意見できなかった。
悔しい、情けないと思った。
でも「怖かった」と感じてたんだな、と思った。
「そんな自分もいる」と認識するだけで、否定のループから一歩抜け出せます。
② 否定の声に名前をつけてみる
次に、自分を責める“内なる声”に意識を向けます。
それは多くの場合、親や先生、過去の経験から刷り込まれた価値観です。
やること:
- 責める言葉を書き出す(例:「ちゃんとしなきゃ」「またできてない」)
- それが誰の影響かを考える
- その声に名前をつけてみる(例:「厳しい先生」)
名前をつけることで、その声と「自分自身」を分けて考えられるようになります。
③ 否定の声に“やさしく”問いなおす
最後は、自分を責める声に対して対話をしてみます。
やること:
- 「それって本当?」「今の自分には合ってる?」と聞く
- 「じゃあ、自分はどうしたい?」と自分の気持ちを見つける
- 「そう思っても大丈夫」と自分に許可を出す
例:
「もっと頑張らなきゃ」→「もう十分頑張ってるかも」
「こんな自分じゃダメ」→「このままでも大丈夫かも」
問いなおしは、否定を消すのではなく、視点を変えるための技術です。
自己受容を続けるために大切なこと
続けるうえで、いくつかのポイントがあります。
意識したいこと:
- 一度で変わろうとしない
- 比べたくなったらSNSから少し離れる
- 自分だけの「許しの言葉」を持つ
- 書く、話す、録音するなど、自分に合った方法を選ぶ
注意点:
- 感情にフタをしない(苦しさを無理にポジティブにしない)
- 「受け入れなきゃ」と自分にプレッシャーをかけない
- うまくできない日があっても、リセットできる
自分のストーリーに気づくと、もっと深く変わる
習慣だけでは届かない部分があります。
それは、「自分はこうあるべきだ」という無意識のストーリーです。
このストーリーこそが、自己否定や不自由さの根っこになっています。
BeYou講座では、このストーリーに光をあてて、
「思い込み」をやさしくほどくプロセスを学びます。
「どうしても受け入れられない私」も、ちゃんと理由があります。
そこに目を向けたとき、本当の変化が始まります。
自己受容できない私が変わった理由
自己受容は、特別な能力ではありません。
小さな問いかけを、少しずつ積み重ねること。
それが、自分を許せる感覚を育ててくれます。
完璧じゃなくていい。
うまくいかない日があってもいい。
そんな自分でも、大切にしていいんだ。
その感覚が、人生のデザインを変えていくはじまりです。
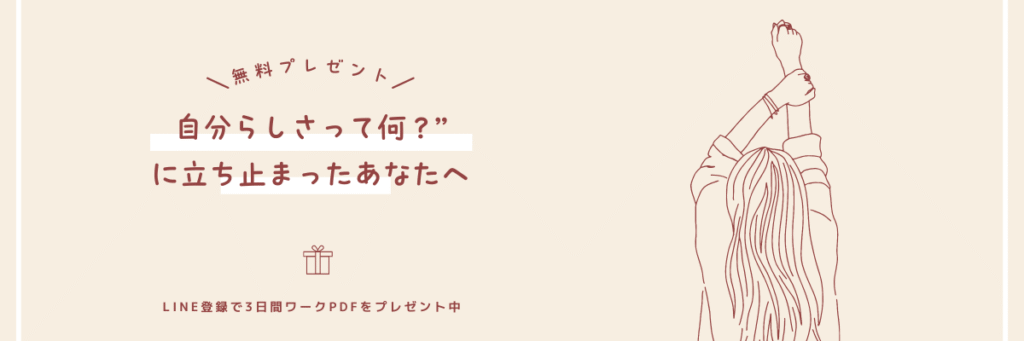

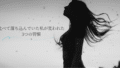
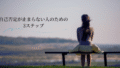
コメント