「やりたいことがあるはずなのに、なぜか動けない」
「今のままじゃ嫌だと思っているのに、変われない」
そんな思いを抱えたまま、日々をやり過ごしていませんか。
行動できない自分を責めたり、もっと頑張らなきゃと焦ったりしてしまうのは自然なことです。
でも、もしかするとその“動けなさ”は、**意志の弱さではなく「感情の抑圧」**から来ているかもしれません。
感情の抑圧とは何か
感情の抑圧とは、本当の気持ちを感じないように無意識にブロックしてしまうことを指します。
たとえば、怒りや悲しみなどの“ネガティブ”とされる感情を「感じてはいけない」と抑え込んでいる状態です。
こうした反応は、ほとんどが自分を守るために起きています。
小さな頃に「泣いたら怒られた」「感情を表に出すのはよくない」と学習した人ほど、感情を感じることに抵抗があります。
感情を抑えるとどうなるのか
感情を無意識に抑え続けると、心の動きが鈍くなっていきます。
その結果、「何がしたいかわからない」「本音が見えない」といった状態に陥りやすくなります。
さらに、慢性的なストレスや疲労感、無気力といった心身の不調にもつながりかねません。
感情の抑圧が積み重なると、自分の感覚や選択力が鈍ってしまうのです。
動けない状態から抜け出す3ステップ
感情の抑圧に気づき、少しずつ手放していくためのシンプルなステップを紹介します。
●ステップ① 「動けない」の奥にある気持ちを探る
「やらなきゃいけないのに動けない」と感じたとき、
それは本当に“やる気がない”からでしょうか。
多くの場合、その奥には以下のような感情が潜んでいます。
例:
・失敗したらどうしようという不安
・どう思われるかが怖いという恐れ
・誰かをがっかりさせたくないという罪悪感
このような感情が、行動のブレーキになっていることがあります。
●ステップ② 自分の感情に「名前」をつけてみる
モヤモヤした気持ちは、そのままにしておくと大きくなります。
そこで効果的なのが、「今、どんな感情があるのか?」と自問し、具体的な名前をつけることです。
例:
・イライラしている
・焦っている
・さみしい
・悲しい
名前がつくと、曖昧だった感情が明確になり、自分の状態を客観的に把握しやすくなります。
●ステップ③ 感じることを「許可」してみる
「こんな感情を持ってはいけない」と思うほど、感情は強く残ります。
反対に、「今はこう感じている」と認めてあげるだけで、その感情はゆっくりと消化されていきます。
ノートにそのままの気持ちを書き出してみましょう。
文章にならなくても大丈夫です。単語でもOKです。
例:
・なんか疲れた
・言いたいこと言えなかった
・ほんとは○○したかった
この作業は、自分に感情を感じることを「許す」小さな第一歩です。
感情を取り戻すと、人生が動き出す
感情を抑え込むことをやめると、自分の“本音”が少しずつ見えてきます。
「本当はこうしたかった」
「これは嫌だった」
その気づきが、自分の選択の軸を取り戻すことにつながります。
行動ができるようになるのは、意志や根性ではなく、感じる力が回復したとき。
それは、感情を押し込めることをやめたときから始まります。
感情の抑圧を手放せば、もう一度「自分」を取り戻せる
感情の抑圧は、かつてのあなたを守ってくれた仕組みです。
でも、これからの人生には、その「感情のフタ」は必要ないかもしれません。
まずは気づくこと。
そして、少しずつ「感じてもいい」と許していくこと。
その積み重ねが、“動けない”日々から抜け出す力になります。
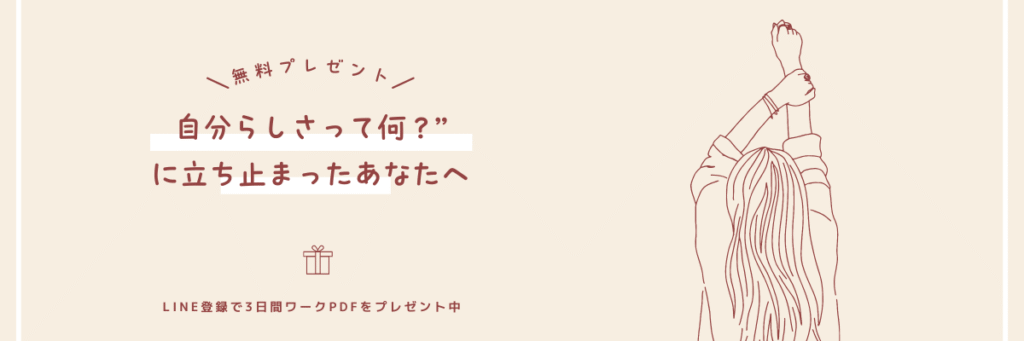
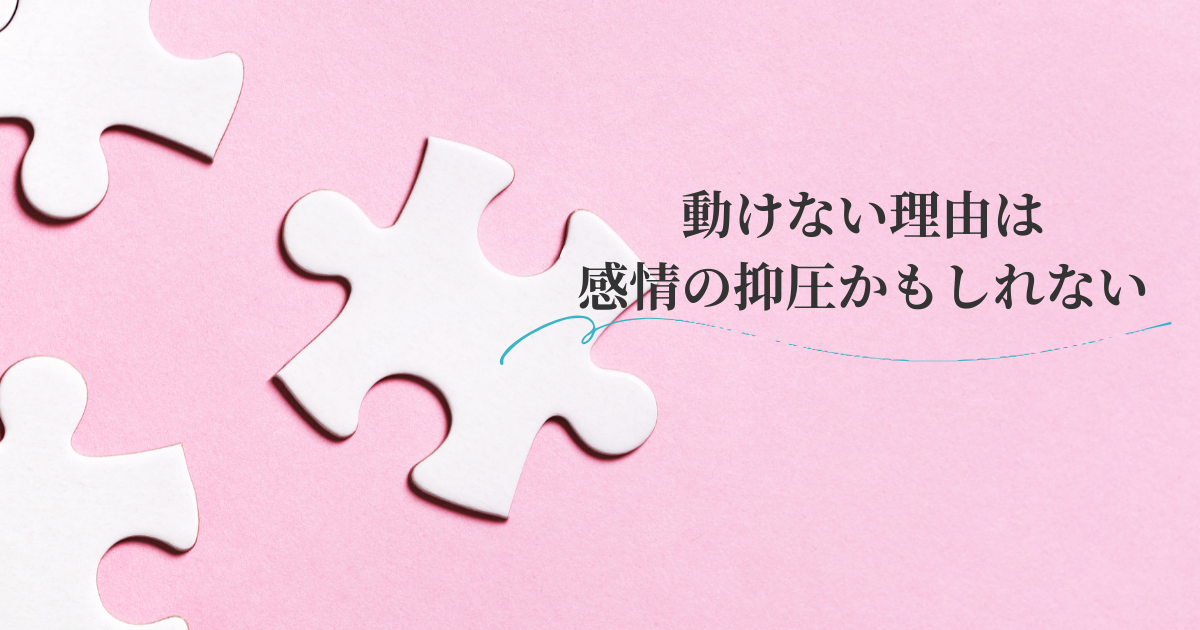
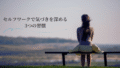
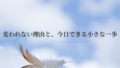
コメント